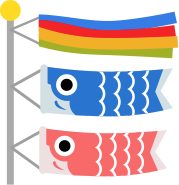厄年
厄年とは、悪いことが身に降りかかりやすい年・人生の節目の年です。一般的に男性は25才、42才、61才、女性は19才、33才、37才が本厄と言い、その前後を前厄(まえやく)・後厄(あとやく)と言います。(厄年の年齢に当たっていなくても、厄祓いはできます。)
地方によっては慣習が異なることがありますので、お近くの神社でお尋ねください。
さあ、神社に行って、厄祓いをしましょう。
令和8年厄年表(数え年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成15年生 (24歳) |
平成14年生 (25歳) |
平成13年生 (26歳) |
| 昭和61年生 (41歳) |
昭和60年生 (42歳) |
昭和59年生 (43歳) |
| 昭和42年生 (60歳) |
昭和41年生 (61歳) |
昭和40年生 (62歳) |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成21年生 (18歳) |
平成20年生 (19歳) |
平成19年生 (20歳) |
| 平成7年生 (32歳) |
平成6年生 (33歳) |
平成5年生 (34歳) |
| 平成3年生 (36歳) |
平成2年生 (37歳) |
昭和64年/平成元年生 (38歳) |
歳祝
い
還暦(かんれき)61才・古希(こき)70才・喜寿(きじゅ)77才・傘寿(さんじゅ)80才・半寿(はんじゅ)81才・米寿(べいじゅ)88才・卒寿(そつじゅ)90才・白寿(はくじゅ)99才・百寿(ひゃくじゅ)100才などの節目には、一家そろって神社にお参りし、長寿をお祝いするのが一般的です。
| 名称 | 年齢 (数え年) |
意味と由来 |
|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 十干十二支が一回りし、生まれた年の干支に戻ることから、本卦還りといい、新たな誕生を祝う |
| 古稀 | 70歳 | 唐の詩人杜甫の「人生七十古来稀なり」という詩が由来 |
| 喜寿 | 77歳 | 喜の草書体が七・十・七に分解できることが由来 |
| 傘寿 | 80歳 | 傘の略字が八・十に分解できることが由来 |
| 半寿 | 81歳 | 半という字が八・十・一に分解できることが由来 |
| 米寿 | 88歳 | 米という字が八・十・八に分解できることが由来 |
| 卒寿 | 90歳 | 卒の旧字体が卆という字で、九・十に分解できることが由来 |
| 白寿 | 99歳 | 百という字から一を引くと九十九になることが由来 |
| 百寿 | 100歳 | 百歳のお祝い。上寿ともいう |